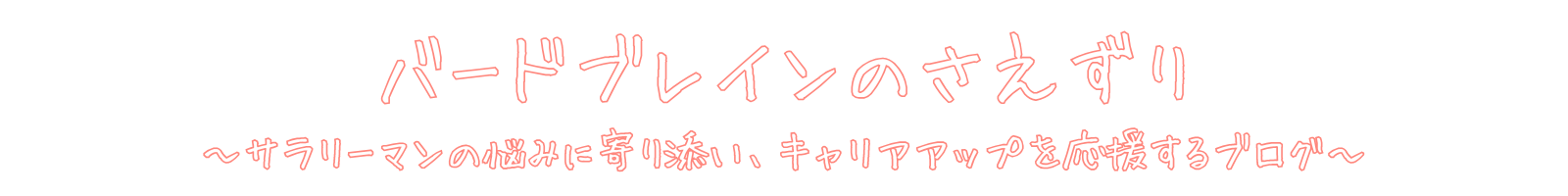最近、「静かな退職」という言葉をよく耳にするようになった。
静かな退職とは、会社に所属しながらも、仕事への意欲を失い、必要最低限の業務のみをこなす働き方である。
私自身、従業員が静かな退職を選択すること自体は、否定されるべきものではないと考えている。社会において、そのような働き方も一つの選択肢として存在し得るからだ。
しかし、もし本人が望まない形で静かな退職を選択せざるを得なくなったとしたら、それは決して好ましい状況とは言えない。
そこで今日は、静かな退職について、私自身の考えをさえずっていこうと思う。
従業員の仕事観タイプ
静かな退職の話をする前に、企業に所属する社員が持つ仕事への考え方や価値観について説明する。
従業員の仕事観は、大きく以下の3つに分類される。
仕事を天職と考える「天職タイプ」
この考え方を持つ人々は、所属する会社や仕事そのものが本当に好きな人達である。
現在の仕事に強い満足感と充実感を覚え、人生を捧げる覚悟さえ持っている。上司から指示された以上の仕事も自ら進んで行い、常に業務改善を試みる意欲も持っている。
天職タイプは仕事を楽しむ一方で、生活との境界線が曖昧になりやすく、時間外労働やサービス残業に抵抗を感じにくい傾向がある。
仕事を成長と考える「成長タイプ」
この考え方を持つ人々は、仕事を通じて自己成長を追求する人達である。
天職タイプとは異なり、仕事を人生そのものとは捉えないが、キャリアアップへの強い意欲を持つため、熱心な社員と見なされることが多い。
指示された業務だけでなく、より良い成果を目指して行動する点も天職タイプと共通するが、その動機は会社への貢献よりも自己成長に重点が置かれる。このため、成長を実感できない仕事には消極的になりがちである。
成長タイプは昇給や昇格などのキャリアアップに強い関心を持つ一方で、会社を自己実現の場と捉える傾向があるため、社内での成長が頭打ちになったと感じると、より大きな成長を求めて転職を検討する。
仕事を労働と考える「労働タイプ」
この考え方を持つ人々は、仕事を生活のための手段と割り切っている人達である。
このタイプの人は基本的にはプライベートを重視しており、仕事は生活を充実させるための必要経費と考える。
労働タイプは仕事においては指示された業務は着実にこなす一方で、それ以上の仕事は極力避け、能力を超える労働には消極的であることが多い。
昇給や昇格への意欲も低く、最小限の労働で十分な収入を得て、プライベートを充実させることを重視する傾向にある。
静かな退職を選ぶのはどのタイプ?
結論から述べると、社員が静かな退職状態になるのは、
天職タイプまたは成長タイプの社員が労働タイプへと価値観を転換した結果である
と私は考えている。
特に、成長タイプが労働タイプに価値観転換するパターンが多いとも考える。
天職タイプや成長タイプは、基本的に成長意欲や労働意欲が高い社員である。仮に能力が他の社員に比べて劣っていたとしても、上司や先輩からは「経験不足なところはあるが、よく頑張っている社員だ」と評価されるだろう。
しかし、そのような意欲的で向上心の高い社員が、急に労働タイプへと価値観を転換したら、周囲はどう見るだろうか?
今までキャリアアップや業務改善に積極的だった社員が、急に労働意欲を失い、仕事へのモチベーションが下がったように見え、周囲からは「急にやる気をなくした」と捉えられるだろう。
これが、私が考える静かな退職の正体である。
静かな退職(価値観の転換)はなぜ起こる?
では、なぜ天職タイプ/成長タイプから労働タイプへの価値観の転換が起きるのだろうか?
その原因はいくつか考えられる。
労働環境や企業文化が入社時の期待値とずれている
多くの従業員は、新たな会社に入社する際、その会社に対して一定以上の期待を持つ。それはどのタイプであっても同様だ。
自ら選び応募し、内定を経て入社を決めているのだから、入社当初は所属する会社に対して自分のタイプに見合った期待を持つものである。
しかし、この期待は必ずしも一致するとは限らない。
例えば成長タイプであれば、入社直後は高い向上心を持ち、自身のスキルを高めるために積極的に業務に取り組もうとするだろう。しかし、その会社や所属組織の労働環境が安定志向であり、単純業務しかなく、自分を成長させる環境でなかったら、徐々に向上心を失ってしまうだろう。
行動力のあるタイプであれば、改めて他社に転職する人もいるかもしれない。しかし、転職活動は体力と時間を要するため、相応のエネルギーが必要な行動だ。
次なる転職活動へのエネルギーがない社員は、そのまま静かな退職(労働タイプへの価値観転換)を選ぶことになるだろう。
個人のキャリアや将来への不安が組織内で改善できない
個人のキャリア形成が現在の労働環境では実現できず、その改善も難しいという場合にも価値観の転換が起こる。
自分のタイプや期待に合った業務に携わりたい場合、通常は上司との会話やコミュニケーションを通じて相互理解を深め、双方の期待を合わせていくものである。
しかし、上司との意思疎通が円滑でなかったり、コミュニケーションの回数が少なかったりすると、相互理解が進まず、結果として期待に合わないチームに所属させられることになったり、望まない業務を指示されたりすることになる。
この状態が続くと、労働タイプへの価値観転換が起きる。
昨今リモートワークが急速に普及し、オフィスワーク時代に比べて上司と部下のコミュニケーションが希薄になっていることも静かな退職の増加に影響していると思われる。
組織の変化や成長に対して社員が適応できない
組織の変化や成長に伴う環境変化によるストレスも、従業員の価値観転換の要因となることがある。
企業や組織が成長することは素晴らしいことだ。また、成長に伴い組織改編やルール改定をしていくことは、成長企業を経営する上で正しい判断であることも間違いない。
しかし、人間は環境の急激な変化に弱い生き物だ。
所属する企業が急な変化を起こし、その変化に従業員が適応できない場合に価値観の転換が起こることがある。それは、急な環境変化に順応できない、変化に対して強いストレスを感じてしまう、などが理由として挙げられる。
これまでの環境であれば、求める業務量やスピード感でキャリアアップができた環境に対し、組織の成長に伴い業務量が増えたり、仕事の幅が広がったり、より早いスピード感が求められるようになることもあるだろう。
そのタイミングで自分のキャパシティを超え、過剰な労働と業務負担によるストレスも増し、いつしか成長タイプから労働タイプへの価値観転換が起きてしまい、結果として静かな退職状態になってしまうことも十分あり得る。
静かな退職は損をする

静かな退職は、自身の社会人人生という貴重な時間を無駄に消費する、タイムパフォーマンスの悪い行為である。労働タイプ以外の価値観を持つ人は、即座に行動を起こし、自身の価値観にあった労働環境に求めるべきだ。
冒頭でも述べたように、私は静かな退職という判断を否定するつもりはない。
なぜなら、静かな退職は「労働タイプ」という価値観を持った状態であり、労働タイプ自体は社会で生きていく上で選択可能な考え方だからである。
しかし、もしあなたが本来「天職タイプ」「成長タイプ」であり、今もその価値観で社会に貢献したいと考えているのであれば、静かな退職を選んでいる間は無駄な時間を消費していると言わざるを得ない。
静かな退職状態は、本来あなたが成長のために使いたい時間を、自ら放棄することに繋がる。
社会人としての成長は、時間がかかるものだ。質の高い業務に携わり、よりレベルの高い業務経験を得ることで、少しずつスキルと経験を積み上げていくものである。
また、その経験は年齢が若ければ若いほど価値が高い。なぜなら、期間の限られた社会人人生の中で、より早い段階でスキルと経験を積み上げていた方が、より長い期間、高いスキルや経験を生かした業務に携わることができるからだ。
当然、社会人人生後半の社会的立ち位置(役職やポジション)にも、静かな退職を選ばなかった人に比べて大きな差が出るだろう。
もしあなたが、望まない静かな退職を選んでしまっているようなら、今すぐ行動を起こすべきだ。
上司との対話の回数を増やし、組織内での業務転換や他部署への移動を打診してみるのもよい。それが叶わないようなら、環境を変えるべく他社への転職活動を始めてみることも必要だろう。
静かな退職状態はある意味『会社が変わってくれることを待っている』状態だ。
時に会社はあなたの期待する通りの会社に変わってくれることもあるが、それは結果論である。会社というものは、個々の従業員に合わせた環境の変化を起こすことはない。
なぜなら、ほぼすべての会社は従業員のためではなく、社会や市場に価値を提供するために存在しているからだ。
従業員はあくまで、その企業の理念や市場価値貢献に賛同し、その価値貢献のために自身の労働力と時間を提供するという従業員契約を結んだだけの関係に過ぎない。
企業には「雇用を守る」という社会における命題があり、また市場価値貢献のために従業員(労働力)を必要としている。このため、会社から率先して従業員の働きやすい環境を提供することもあるだろうが、会社の本質は従業員の働き方改善ではなく、社会への価値貢献であることを忘れてはいけない。
まとめ
今回は静かな退職について、自分なりの考えをさえずってみた。
静かな退職という状態は、価値観の転換に伴う結果であると私は考えている。
元々が労働タイプである人が、低い意欲で必要最低限の業務しか行わないことは、静かな退職とは言わない。それも働き方の一種であると考えているからだ。
しかし、本来天職タイプや成長タイプである人が、望まない形で労働タイプを選ばなければならなくなった場合は、それは静かな退職状態だ。
望まない静かな退職は、皆さんのキャリア形成にとって非常にもったいない状態であるため、少しでも早く改善のための行動を起こすことを私は望んでいる。